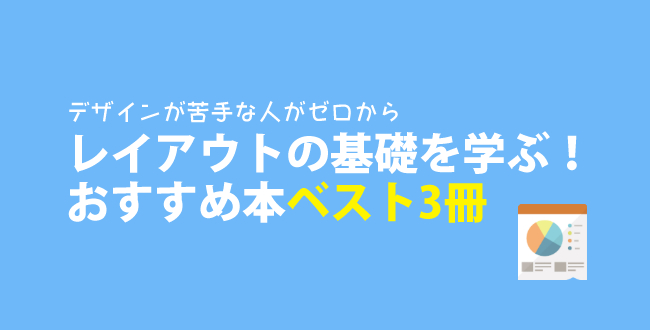
デザインとかレイアウトとか苦手!センスない!いつまで経っても初心者です!
そんな筆者が基礎を学んだり、すぐに活用できると感じた便利なデザイン関連書籍のTOP3をランキング化しました。
今後増えるかも?
流行で変わらない普遍的なデザインの基礎を扱っていて簡単なものを選びました。
1位:伝わるデザインの基本 良い資料をつくるためのレイアウトのルール
※好評につき、増補改訂版が出たみたいです!
筆者は旧版を使っているので内容紹介の画像はすべて旧版のものになります。
どんな本?
・デザインと無縁の理系学生・研究者やサラリーマンでもわかる本
・シンプルですぐに実践に取り入れやすい例が多い
・デザインの法則を基礎から学べる
「これがかっこいいよ」だけでなく、きちんと根拠を示したうえで、
「どうしてこうしたほうがいいのか?」が解説されているのが最大の特徴。
ですのでデザインに関してまったくの初心者が読んでも、
配置の仕方やバランスの法則や理由から論理的に学習できますし、
自分の中にレイアウトの成功パターンを作ることができます。
とくに「レイアウトのレの字もわかんねえよ!」って人は、
まずはこの本から取り組むと目からウロコがぼろぼろ落ちます!
WordやPowerPointでも使えるような基礎的な機能をベースにかかれているので
デザインソフトを持っていなくても活用できるのも魅力。
デザイン系の学生やデザイナーになったけど基礎がちょっと不安…
という人の入門書としてもオススメ。
元デザイン系学部出身の私もずっとバイブル代わりに愛用しています。
デザイン関連の本の中には辞書みたいな厚さで読む前からうんざりする本も多いので、
分厚くなくて無駄がないのがいいんですよね。
ではさっそく詳しい内容の紹介にうつります。
こんなデザインが出来るようになります
この本では、
デザイナーではない人のためのデザインルール
(P8 より)
と掲げていて、解説項目も初歩的でとっつきやすい部分を中心に書かれています。
1章から順を追って学習してもいいですし、
実際に制作している時に困った箇所を逆引き的に参照するという使い方もできます。
以下、書籍の内容を章ごとにご紹介します!
どんなフォント(書体)を選べばいいかの基準、
おすすめのフォント、数字と英文が混ざるときのデザイン法則などのレクチャー。
「50%の「%」を小さくすると数字が読みやすくなる」
これならデザインが苦手な人にも分かりやすいですね。
2行以上の文章のレイアウト方法のレクチャーをしています。
行間、字間はどれくらいが適切か、
改行の適切な箇所、見出しの付け方、
タイトルに対して内容のフォントサイズはどれくらいがいいかなど、
すぐにでも使える知識が満載。
図や表の作り方や、それをどう配置したらいいかを解説しています。
これらのオブジェクトの装飾のルール(派手ならいいわけじゃない!)とか、
矢印の綺麗な使い方、図に見やすい説明をつける方法、
折れ線や円形のグラフの作り方も掲載されています。
これまでの章をもとに、紙面全体のレイアウトの仕方を解説。
揃えて配置・グループ化・繰り返し…など、
なるべく専門用語を使わずにレイアウトで使えるデザイン法則を紹介しています。
また、わかりやすくするための色の選び方も。
なんと色盲・色弱の方にも配慮した色選びの方法まで掲載されています!
最後は実際に使えるサンプル例のコーナー。
プレゼンのスライド、発表資料、発表ポスター、
文書書類、チラシ、カタログなど、多岐にわたっています。
ここには「悪い例」「失敗例」と、
「どこがダメか?」も掲載されているので、
とりあえず作りたいものが決まっている人はここを最初に参考にするのもアリ。
2位:レイアウトの基本ルール 作例で学ぶ実践テクニック
どんな本?
・フォントサイズやここが何mmなどの具体的な数字が掲載
・初心者は真似するだけで整った物を作れる
・前半部分には用紙サイズやソフトの紹介などデザインの教科書的要素も
考えるのが面倒だけど、綺麗なもの作りたい!という人にはうってつけの本です。
とにかくこの本の作例のとおりにマネをして制作すれば、
デザインが苦手な人でも整ったものが作れるというすぐれもの。
2位にしたのは、デザイン用のソフトを使う前提で書かれている部分が多いので、
ゼロから学ぶという趣旨でいうと『伝わるデザインの基本』には負けるかな?という理由です。
こんなデザインが出来るようになります
1位の『伝わるデザインの基本』の解説よりも、さらにデザインの知識に踏み込んだ内容です。
1つの内容が見開きでまとめられていてとてもコンパクト。
画像補正(明るさなど)の説明もあります。
これに加えて、「紙モノ」のサイズ表が付いていて大変便利です。
はがきやA4以外に、各種封筒のサイズまで載っています。
また、IllustratorやInDesignなどのデザインソフトについての紹介もあります。
名刺やチケット等、各作例ごとに適した注意点をわかりやすく1ページで解説してあります。
その後に実際の作例をフォントの種類や余白のサイズと共に詳しく掲載しています。
3位:マネするだけでエディトリアルデザインが上手くなるはじめてのレイアウト
どんな本?
・Adobe InDesign使用者を主なターゲットとした教科書的な本
・レイアウト失敗例の紹介もある
エディトリアルデザインとは新聞・雑誌・書籍などの出版物の中身のレイアウトデザインのこと。
エディトリアル=編集という意味。
どちらかというと、ガイドブックやパンフレット、マニュアルなどの文章が多い制作物を作るときに使える本です。
InDesignで使えるような事細かい数字(単位Qやmmなど)で作例を大きく掲載しているので、
どんな仕上がりになるかが分かりやすいです。
反面、法則については少し専門的な解説が多いので、
まったくデザインソフトなどを触ったことがないと理解が追いつかない場合があるかも。
このため他の2冊に比べて順位は3位としました。
こんなデザインが出来るようになります
作例と作例の間に解説が挟まる形式です。
TIPSでは「マネするだけで上手くなる3つのポイントの紹介」などが解説されています。
実際の作例(1ページ分や見開き)が他の本に比べ大きめに掲載されていて、
完成形が想像しやすいのが利点。
1段組・2段組や奥付の作り方などの作例もあるので、
小説や新書など、文章量の多い冊子を作りたい場合には向きます。
その他のおすすめ本
文章多めの本を作りたいときなど、
文字組みやエディトリアルデザインを知りたい場合は以下の記事で紹介している「文字の組み方ルールブック」シリーズもいいですよ~!
こちらは完全に作家さんや編集さん向けのテキスト編集作法についての教科書です。
今回紹介したデザイン書籍は上の同人誌を作ろう記事でもおすすめしていて、
重複しているのですが、それほどに使い勝手がいいんですよね。
これからデザインを勉強したい人もそうですし、
「デザインについて勉強までしてる時間はないけど、資料を綺麗にまとめたい…」という人には確実に役立つこと請け合いです。
小説とかなら縦組み、発表資料とかならヨコ組です!





